 採尵俇俉丗OECD 惗搆偺妛廗摓払搙俀侽侾俀擭挷嵏偺寢壥偲壽戣丂丂丂丂 採尵俇俉丗OECD 惗搆偺妛廗摓払搙俀侽侾俀擭挷嵏偺寢壥偲壽戣丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂丂丂丂乣 妛椡僩僢僾俁偲偺嵎傪夝徚偡傞曽嶔偼丠 乣
丂搶嫗搒嫵堢夛偼丄偙傟傑偱OECD偑恑傔偰偒偨PISA乮Program for International Student Assessment乯丄偄傢備傞丄崙嵺揑側妛廗摓払搙偵娭偟偰俁夞偺採尵傪峴偭偨丅
丂侾夞栚偼乽採尵俀丗偙傟偐傜媮傔傜傟傞妛椡乿丄俀夞栚偼乽採尵俇丗妛傇堄梸傪堷偒弌偡嫵堢傪亅OECD PISA寢壥偺峫嶡傪摜傑偊偰亅 乿丄俁夞栚偼乽採尵俀俋丗俀侽侽俋擭偺崙嵺挷嵏偲壽戣乿偱偁傞丅
丂 PISA挷嵏偱偼丄侾俆嵨帣傪懳徾偵悢妛揑儕僥儔僔乕丄撉夝椡丄壢妛揑儕僥儔僔乕偺俁暘栰偵偮偄偰丄俁擭偛偲偵杮挷嵏傪幚巤偟偰偄傞丅
丂 俀侽侾俀擭偺PISA偺寢壥偼丄俀侽侾俁擭侾俀寧俁擔偵敪昞偝傟偨丅崱夞偺挷嵏偵偼丄俇俆僇崙丒抧堟乮OECD壛柨俁係僇崙丄旕壛柨俁侾僇崙乯偺侾俆嵨抝彈栺俆侾枩恖偑嶲壛偟偨丅擔杮偼崱夞丄柍嶌堊偵拪弌偝傟偨栺俇係侽侽恖偺崅峑侾擭惗偑僥僗僩傪庴偗偨丅
丂岞昞寢壥偵傛傞偲丄OECD壛柨俁係僇崙偺暯嬒傪俆侽侽揰偲姺嶼偟偨応崌偺擔杮偺摼揰偼丄悢妛揑儕僥儔僔乕偑俆俁俇揰丄撉夝椡偑俆俁俉揰偱夁嫀嵟崅傪婰榐丄壢妛揑儕僥儔僔乕偑俆係俈揰丄偄偢傟傕慜夞挷嵏偺摼揰傪戝偒偔忋夞偭偨丅崙丒抧堟暿弴埵傕俀侽侽俋擭
偵懕偄偰俀夞忋徃偟偨丅擔杮偺惗搆偺妛椡偼岦忋偟偰偒偨丅
丂偦偙偱丄戞侾夞挷嵏乮俀侽侽侽擭乯偐傜戞俆夞乮俀侽侾俀擭乯傑偱偺寢壥偲宱堒偵怗傟側偑傜丄崱屻偺壽戣偵偮偄偰弎傋偰傒偨偄丅丂
侾丏偙傟傑偱偺崙嵺妛廗摓払搙挷嵏寢壥偲宱堒
丂PISA偼俀侽侽侽擭偵巒傑偭偨丅嶲壛崙偑嫟摨偱崙嵺揑偵奐敪偟丄幚巤偟偰偄傞侾俆嵨帣傪懳徾偲偡傞妛廗摓払搙挷嵏偱偁傞丅俁擭偛偲偵幚巤偝傟丄悢妛揑儕僥儔僔乕丄撉夝椡丄壢妛揑儕僥儔僔乕偺俁暘栰偵偍偗傞挷嵏偱偁傞丅枅夞俁暘栰偺偆偪侾暘栰傪廳揰揑偵挷嵏偡傞偙偲偵側偭偰偄傞丅俀侽侾俀擭偼悢妛揑儕僥儔僔乕偑廳揰崁栚偲側偭偨丅
丂乮侾乯擔杮偺妛椡 悽奅戞侾埵帪戙
丂峀搰戝妛柤梍嫵庼 晲懞廳榓巵偼丄弶摍嫵堢尋媶強夛曬俁俉崋偵偍偄偰丄乽妛椡悽奅戞侾埵帪戙偺棟壢嫵堢乿偲戣偟偰丄乽侾俋俈侽擭戙偲侾俋俉侽擭戙偺弶傔偵崙嵺嫵堢摓払搙昡壙妛夛乮IEA乯偵傛傞崙嵺悢妛丒棟壢嫵堢挷嵏乮TIMSS乯偵偍偄偰丄変偑崙偺侾侽嵨帣偑妛椡悽奅戞侾埵偵側傝丄俀侽擭娫偦偺抧埵偼梙傞偑側偐偭偨丅乿偲婰弎偟偰偄傞丅
丂傑偨丄PISA俀侽侽侽擭挷嵏寢壥偵偍偄偰傕丄擔杮偼悢妛揑儕僥儔僔乕偑侾埵丄撉夝椡偑俉埵丄壢妛揑儕僥儔僔乕偑俀埵偱偁偭偨丅
丂偙偺傛偆偵丄乽PISA丄TIMSS乮拲侾乯乿丄偺寢壥偐傜侾俋俈侽擭戙偐傜俀侽侽侽擭傑偱偺俁侽擭娫丄擔杮偺帣摱惗搆偺妛椡偼悽奅偺僩僢僾僋儔僗偱偁偭偨偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅
丂乮俀乯PISA僔儑僢僋
丂俀侽侽侽擭挷嵏偱偼丄侾埵偩偭偨悢妛揑儕僥儔僔乕偑俀侽侽俁擭偵偼俇埵丄壢妛揑儕僥儔僔乕偑俀埵偐傜俀埵偲弴埵偼曄傢傜側偐偭偨偑丄摼揰偼俆俆侽揰偐傜俆係俉揰偲俀揰掅壓偟偨丅撉夝椡偑俉埵偐傜侾俆埵丄慡暘栰偱弴埵傪壓偘偨丅惉愌偑尙暲傒僟僂儞偟偨丅
丂俀侽侽俇擭挷嵏寢壥偱偼丄擔杮偼丄悢妛揑儕僥儔僔乕偑侾侽埵丄撉夝椡偑侾俆埵丄壢妛揑儕僥儔僔乕偑俇埵偲慡暘栰偱丄俀侽侽俁擭傛傝傕弴埵傪壓偘偨丅妛椡偑悽奅偺僩僢僾儗儀儖偐傜揮棊偟偨偙偲偑柧妋偵側偭偨丅
丂俀侽侽俁丒俀侽侽俇擭偺挷嵏寢壥傪庴偗偰丄嫵堢娭學幰偵偼乽PISA僔儑僢僋乿乮拲俀乯偲偄偆尵梩偱丄擔杮偺帣摱惗搆偺妛椡掅壓偑栤傢傟傞傛偆偵側偭偨丅丂
丂暥晹壢妛徣傕乽傢偑崙偺妛椡偼悽奅僩僢僾儗儀儖偲偼尵偊側偄乿偲婋婡姶傪嫮傔偨丅偦偟偰丄俀侽侽俆擭偵乽撉夝椡岦忋僾儘僌儔儉乿傪嶔掕偟丄PISA偲椶帡栤戣傪弌偡乽慡崙妛椡挷嵏乿偺奐巒乮俀侽侽俈擭乯摍偺惌嶔傪懪偪弌偟偨丅
丂俀侽侽俇擭偺挷嵏懳徾偲側偭偨崅峑侾擭偺惗搆偼丄媗傔崬傒嫵堢偐傜偺扙媝傪恾偭偨乽備偲傝嫵堢乿傪宖偘偨妛廗巜摫梫椞偺壓偱丄彫妛峑俇擭惗偺帪偐傜庼嬈傪庴偗偰偒偨悽戙偱偁傞丅乽惗偒傞椡乿傪堢傓偲偄偆棟擮偵婎偯偄偰乽妋偐側妛椡乿傪堢惉偡傞嫵堢偱偁偭偨偑丄廩暘側妛椡偼恎偵偮偐側偐偭偨丅
丂乮俁乯PISA僔儑僢僋偐傜偺扙弌 丂
丂乽PISA僔儑僢僋乿偐傜偺棫偪捈傝傪栚巜偟丄暥晹壢妛徣傪偼偠傔丄嫵堢埾堳夛丄嫵堢尰応丄偦傟偧傟偑妛椡岦忋傪栚巜偟偰昁巰偵搘椡傪偟偰偒偨丅偦偺寢壥丄俀侽侽俋擭偺挷嵏偱偼丄悢妛揑儕僥儔僔乕偑俋埵乮俀侽侽俇擭侾侽埵乯丄撉夝椡偑俉埵乮俀侽侽俇擭侾俆埵乯丄壢妛揑儕僥儔僔乕偑俆埵乮俀侽侽俇擭俇埵乯偲丄慜夞傛傝惉愌偑忋偑偭偨丅
丂俀侽侽俈擭偐傜彫妛俇擭惗偲拞妛俁擭惗慡堳傪懳徾偵巒傑偭偨慡崙妛椡僥僗僩偱偼丄乽俙栤戣乿偺傎偐丄PISA偑應傞妛椡傪堄幆偟偨乽俛栤戣乿偱妶梡椡傪傒傞栤戣偑弌戣偝傟偨丅
丂俀侽侽俋擭搙偐傜愭峴幚巤偝傟偨彫拞妛峑偺怴妛廗巜摫梫椞偱棟壢偲嶼悢丒悢妛偺妛廗撪梕傗庼嬈帪悢偑憹偊偨偙偲傕丄嫵堢尰応傊偺巋寖偲側偭偨偲峫偊傜傟傞丅
丂俀侽侾侾擭搙埲崀丄妛廗撪梕偑戝暆偵憹壛偟偨怴妛廗巜摫梫椞偑慡柺幚巤偝傟偨丅偄傢備傞丄乽嫵堢婎杮朄偺栚昗乿傗乽抦幆婎斦幮夛乿偺幚尰傪崻杮揑側惛恄偲偡傞怴偨側棟擮傗撪梕偺峔憿偑柧妋偵帵偝傟偨丅摿偵丄廗摼宆丒妶梡宆丒扵媮宆偺嫵堢偺悇恑傪宖偘丄庼嬈偺夵慞偵搘傔丄PISA偺妛椡娤偵婎偯偄偨嫵堢偺悇恑偑廳帇偝傟傞傛偆偵側偭偨丅
丂偟偐偟丄俀侽侽俋擭偺崙嵺妛椡挷嵏偵偍偄偰傕丄夵慞偝傟偰偄側偄壽戣偑偁偭偨丅廗弉搙偲屇偽傟傞儗儀儖乮妛椡偺奒憌乯偵偍偗傞惉愌偺暘晍撪梕偱偁傞丅乽幮夛惗妶傪塩傓忋偱巟忈傪偒偨偡儗儀儖侾埲壓乿偲偝傟傞掅妛椡憌偺妱崌偑丄擔杮偼俁偮偺暘栰偲傕侾侽亾傪挻偊偰偄偨丅妛椡忋埵侾侽偐崙丒抧堟偺拞偱傕偦偺妱崌偑崅偐偭偨丅惉愌偺椙偄惗搆偲掅偄惗搆偺擇嬌壔偺孹岦偑昞弌偟偰偒偨傛偆偵傕峫偊傜傟傞丅擇嬌壔偺崻嫆偲偟偰壠掚偺宱嵪椡偺嵎偑妛椡嵎偵寢傃偮偄偰偄傞偲偄偆尒曽傪偡傞嫵堢娭學幰傕彮側偔側偄丅偦傟偑帠幚偲偡傟偽丄宱嵪奿嵎偺夝徚傪恾傜側偗傟偽丄惗搆偺妛椡傪崅傔傞偙偲偼擄偟偄丅丂
俀丏PISA俀侽侾俀擭挷嵏偺寢壥偲壽戣 丂
丂PISA俀侽侾俀擭挷嵏偺寢壥偼丄忋奀偑慜夞偵堷偒懕偒丄俁暘栰偡傋偰偵偍偄偰僩僢僾偱偁偭偨丅忋奀丄崄峘丄僔儞僈億乕儖偺俁僇崙丒抧堟偑僩僢僾俁傪撈愯偟偨丅堦曽丄偙傟傑偱奺暘栰偱侾埵丄俀埵傪撈愯偟偰偄偨僼傿儞儔儞僪偑弴埵傪棊偲偟偨丅悢妛揑儕僥儔僔乕偼弶傔偰侾侽埵埲壓偵屻戅偟偨丅嫵堢嵞惗幚峴夛媍偑俀侽侾俁擭俆寧偵傑偲傔偨戞俁師採尵偱偼丄彫丒拞丒崅峑偺抜奒偐傜僌儘乕僶儖壔偵懳墳偟偨嫵堢傪廩幚偝偣傞偨傔丄彫妛峑偱偼乽幚巤妛擭偺憗婜壔丄巜摫帪娫憹丄嫵壢壔丄愱擟嫵堳攝抲摍乿偵傛傞塸岅妛廗偺敳杮揑奼廩傪峴偆傛偆採埬偟偨丅
丂僼傿儞儔儞僪偑奺暘栰偱侾埵丄俀埵傪撈愯偟偰偄偨摉帪丄僼傿儞儔儞僪偺嫵堢偵拲栚偑廤傑傝丄擔杮偐傜傕嫵堢娭學幰偑僿儖僔儞僉傪朘傟傞偙偲偑懡偐偭偨丅僼傿儞儔儞僪偼丄崅暉巸丒崅晧扴傪巟偊傞岞嫟偺惛恄傪堢傓嫵堢傪廳帇偟偰偄傞丅乽嫵堢偙偦偑崙壠偺婱廳側帒嶻乿偲偟偰丄帣摱惗搆偺岲婏怱傪堷弌偟丄妛媺撪偱偼妛椡嵎偵墳偠偨屄暿巜摫傪揙掙偟偰偄傞丅嫵堳偺幮夛揑抧埵丄怣棅偺崅偝偼丄嫵怑傪嵟傕桪廏側恖偑廇偔怑嬈偲偟偰偄傞丅
丂俀侽侾俀擭偺丂擔杮偺暯嬒揰偼乽悢妛揑儕僥儔僔乕乿乽撉夝椡乿乽壢妛揑儕僥儔僔乕乿偺慡俁暘栰偱俀侽侽侽擭偺挷嵏奐巒埲崀偱嵟傕崅偔丄弴埵傕慜夞傪忋夞偭偨丅
丂OECD壛柨崙乮俁係僇崙乯偩偗偱斾傋傞偲丄擔杮偼撉夝椡偲壢妛揑儕僥儔僔乕偼侾埵丄悢妛揑儕僥儔僔乕偼係埵偱偁偭偨丅
丂廗弉搙儗儀儖乮拲俁乯偱偼丄乽悢妛揑儕僥儔僔乕乿偲乽壢妛揑儕僥儔僔乕乿偼丄俈抜奒丄乽撉夝椡乿偼俉抜奒偵暘偗傜傟偰偄傞丅擔杮偺惗搆偺惉愌偼壓埵憌乮儗儀儖侾枹枮乯偺妱崌偼奺暘栰偱尭彮偟丄忋埵憌乮儗儀儖俇埲忋乯偺妱崌偼奺暘栰偱憹壛偟偨丅
俀侽侾俀擭崙嵺妛廗摓払搙挷嵏偱偼丄廳揰挷嵏懳徾偺悢妛揑儕僥儔僔乕偵偮偄偰丄惗搆偺嫽枴傗栚揑堄幆摍傪栤偆堄幆挷嵏傕峴傢傟偨丅丂
丂乮侾乯擔杮偺惗搆偺妛椡夞暅
丂PISA俀侽侽侽擭乣俀侽侾俀擭偺擔杮偺摼揰傪僌儔僼偱帵偡偲壓婰偺捠傝偱偁傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
OECD丂PISA挷嵏偺宱堒乮昅幰嶌惉乯
丂俀侽侾俀擭PISA偵嶲壛偟偨俇俆僇崙丒抧堟乮OECD壛柨俁係僇崙丄旕壛柨俁侾僇崙乯偺拞偱丄擔杮偼悢妛揑儕僥儔僔乕俈埵乮慜夞俋埵乯丄撉夝椡係埵乮慜夞俉埵乯丄壢妛揑墳梡椡係埵乮慜夞俆埵乯偲忋埵偵擖偭偨丅丂
丂PISA俀侽侽俇擭偺挷嵏偱偼弴埵偑媫棊偟偨丅強堗乽PISA僔儑僢僋乿傪宊婡偵丄乽備偲傝嫵堢乿偐傜偺揮姺傪偼偠傔丄妛峑偵偍偄偰傕栤戣夝寛傪恾傞庼嬈丄扨側傞埫婰椡傗寁嶼椡偱偼側偔丄抦幆偺妶梡椡傗昞尰椡傪怢偽偡PISA宆偺妛廗偑峴傢傟傞傛偆偵側偭偨偐傜偩偲峫偊傜傟傞丅丂
丂暥晹壢妛徣偼丄妛廗巜摫梫椞偺夵掶傗彮恖悢巜摫偺晛媦摍乽扙備偲傝乿偺巤嶔偑岲惉愌偺梫場偲傒偰偄傞丅偄傢備傞乽備偲傝嫵堢乿偐傜扙媝偟丄妋偐側妛椡傪堢惉偡傞庢傝慻傒偑丄妛椡偺暅妶偵宷偑偭偨偲峫偊傜傟傞丅
丂偟偐偟丄奺崙偺暘栰暿暯嬒揰乮忋婰偺昞乯偱暘偐傞傛偆偵丄僩僢僾侾偺忋奀偺摼揰偲斾妑偡傞偲丄悢妛揑儕僥儔僔乕偱俈俈揰丄撉夝椡偱俁俀揰丄壢妛揑儕僥儔僔乕偱俁俁揰傕奐偒丄偦偺嵎偼偐側傝戝偒偄丅
丂忋奀偺惉愌偵偮偄偰偼丄採尵宆僯儏乕僗僒僀僩偺乽BLOGOS乿偺俀侽侾俁擭侾俀寧俁擔偺僯儏乕僗偱丄乽拞崙偼崙壠偺埿怣傪偐偗PISA偵椪傒丄拞崙偺拞偱傕嵟愭抂傪峴偔忋奀巗偺恑妛峑偐傜慖傝偡偖傝偺惗搆傪嶲壛偝偣偰偄傞偲僂儚僒偝傟傞丅乿偲婰弎偟偰偄傞丅偟偐偟丄偦偺摼揰嵎傪弅傔傞搘椡偼昁梫偱偁傞丅傑偨丄僩僢僾俁偵忋奀丄崄峘丄僔儞僈億乕儖偺傾僕傾惃偑愯傔偰偄傞偙偲傕丄尒摝偡偙偲偼偱偒側偄丅擔杮偺惗搆偺惉愌傪偝傜偵岦忋偝偣丄僌儘乕僶儖壔幮夛偱惗偒敳偔椡傪恎偵晅偗偰偄偔偙偲偑廳梫偱偁傞丅
丂乮俀乯廗弉搙儗儀儖偵偍偗傞壽戣
丂壓婰偼擔杮偺廗弉儗儀儖暿偺惗搆偺妱崌傪帵偡僌儔僼偱偁傞丅乮崙棫嫵堢惌嶔尋媶強乽OECD 惗搆偺妛廗摓払搙挷嵏 亅俀侽侾俀擭挷嵏崙嵺寢壥偺梫栺乿傛傝堷梡乯
丂丂丂丂擔杮偺廗弉搙儗儀儖暿偺惗搆偺妱崌乮宱擭曄壔乯悢妛揑儕僥儔僔乕
丂丂丂丂擔杮偺廗弉搙儗儀儖暿偺惗搆偺妱崌乮宱擭曄壔乯撉夝椡
丂丂丂丂擔杮偺廗弉搙儗儀儖暿偺惗搆偺妱崌乮宱擭曄壔乯壢妛揑儕僥儔僔乕
丂忋婰偺僌儔僼偐傜暘偐傞傛偆偵丄俀侽侾俀擭偺挷嵏偵傛傞擔杮偺惗搆偺廗弉搙偼丄奺暘栰偱嵟壓埵憌乮儗儀儖侾枹枮乯偺妱崌偑尭彮偟丄嵟忋埵憌乮儗儀儖俇埲忋乯偺妱崌偑憹壛偟偨丅摼揰偺忋徃偵敽偄丄廗弉搙偵偍偗傞忋埵憌偺妱崌偑憹壛偟偨偙偲偼丄妛椡偺岦忋孹岦偑慛柧偵側偭偨偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丄僩僢僾俁乮忋奀丒崄峘丒僔儞僈億乕儖乯偲偺嵎偲偦偺梫場傪暘愅偟丄専摙偟偰偄偔偙偲偑廳梫偱偁傞丅
丂嘆丂悢妛揑儕僥儔僔乕
丂擔杮偺惗搆偺栺11亾偼丄悢妛揑儕僥儔僔乕偺儀乕僗儔僀儞偱偁傞儗儀儖2偵払偟偰偄側偄丅偙偺儗儀儖偺惗搆偼丄侾偮偺壽戣偐傜娭楢忣曬傪摼偰丄帺慠悢傪娷傓栤戣傪夝偔偨傔偵婎杮揑側寁嶼丄岞幃丄庤弴傗曽朄傪巊偆偙偲偑偱偒傞掱搙偱偁傞丅
丂擔杮偺惗搆偺栺24%偼丄悢妛揑儕僥儔僔乕偺嵟忋埵偺廗弉搙乮儗儀儖5丄6乯偵払偟偰偄傞丅偙偺儗儀儖偵払偟偨惗搆偼丄廮擃側巚峫傗悇榑偺椡傪巊偄側偑傜丄栤戣夝寛偵庢慻傓偙偲偑偱偒傞偲尵偊傞丅偟偐偟丄忋奀偺55亾偺惗搆偼偙偺儗儀儖偵払偟偰偄傞丅傑偨丄崄峘丒僔儞僈億乕儖偱偼丄3係亾乣40亾偺惗搆偑偙偺儗儀儖偵払偟偰偄傞丅擔杮偼僩僢僾俁偺傾僕傾惃傪栚昗偵丄惉愌岦忋傊偺搘椡偑昁梫偱偁傞丅摿偵丄悢妛傪偳偺傛偆偵幚惗妶偵妶梡偡傞偐摍丄偙偺壽戣夝寛傪栚巜偟偰丄庼嬈偺夵慞偲廩幚傪恾偭偰偄偔偙偲偑廳梫偱偁傞丅
丂嘇丂撉夝椡
丂擔杮偺惗搆偺栺10亾偼丄撉夝椡偲偟偰儀乕僗儔僀儞偺儗儀儖2偵払偟偰偄側偄丅偙偺儗儀儖偺惗搆偼丄側偠傒偺偁傞榖戣偺暥復偵偍偄偰拞怱僥乕儅傗嶌幰偺栚揑傪擣幆偟丄暥復拞偺忣曬偲擔忢惗妶偺抦幆偺娫偺娙扨側寢傃晅偗偑偱偒傞掱搙偱偁傞丅
丂擔杮偺惗搆偺栺18%偼丄撉夝椡偺嵟忋埵偺廗弉搙乮儗儀儖6乯偵払偟偰偄傞丅偙偺儗儀儖偺惗搆偼丄側偠傒偺側偄宍幃傗撪梕偺暥復傪埖偄丄偦偺暥復偺徻嵶側暘愅傪峴偆偙偲偑偱偒傞丅2000擭偐傜俉丏俆億僀儞僩憹壛偟偰偄傞丅堦曽丄忋奀偺俀5亾丄崄峘丒僔儞僈億乕儖偱偼丄侾俈亾乣俀侾亾偺惗搆偑偙偺儗儀儖偵払偟偰偄傞丅
丂撉夝椡偵偍偄偰偼丄妛椡忋埵憌偑傾僢僾偟偨偲摨帪偵丄壓埵憌傕掙忋偘偝傟偨偐傜偱偁傞丅崱屻偼丄僥僉僗僩傪棟夝偟丄棙梡偟丄弉峫偟丄妶梡偟偰偄偔擻椡傪崅傔傞庼嬈偵夵慞偟偰偄偔偙偲偑昁梫偱偁傞丅
丂嘊丂壢妛揑儕僥儔僔乕
丂擔杮偺惗搆偺栺8亾偼丄壢妛揑儕僥儔僔乕偲偟偰儀乕僗儔僀儞偺儗儀儖俀偵払偟偰偄側偄丅偙偺儗儀儖偺惗搆偼丄梌偊傜傟偨帠幚偵婎偯偄偰丄壢妛揑側愢柧傪偡傞偙偲偑弌偒傞掱搙偱偁傞丅偟偐偟丄2006擭偐傜4億僀儞僩尭彮偟偰偄傞偙偲偼丄儗儀儖俀埲忋偺憌傊堏峴偟偨偐傜偱偁傞丅
丂擔杮偺惗搆偺栺18%偼丄壢妛揑儕僥儔僔乕偺嵟忋埵偺廗弉搙乮儗儀儖5丄6乯偵払偟偰偄傞丅偙偺儗儀儖偺惗搆偼丄壢妛揑抦幆傗暋嶨側擔忢惗妶偵偍偗傞壢妛偵娭偡傞抦幆偵偮偄偰丄婥晅偒丄愢柧偟丄揔梡偡傞偙偲偑偱偒傞丅堦曽丄忋奀偺俀俈亾丄僔儞僈億乕儖偺俀俁亾惗搆偼偙偺儗儀儖偵払偟偰偄傞丅崄峘偺惗搆偼侾俈亾偱偁傝丄擔杮偺惗搆傛傝侾億僀儞僩掅偐偭偨偑丄崱屻偼丄壢妛揑側帠徾傪妉摼偟偨抦幆偵婎偯偄偰丄夝庍偟愢柧偑弌偒傞傛偆偵丄傑偨怴偨側抦偺憂憿傪栚巜偡庼嬈夵慞傪偡傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅
丂乮俁乯俁暘栰偺惓摎棪丒柍摎棪
丂 PISA僔儑僢僋乮俀侽侽俁擭乣俀侽侽俇擭乯偐傜偺棫偪捈傝傪栚巜偟丄妛峑偱偼廗摼偟偨抦幆偺妶梡丄廮擃側巚峫椡傗昞尰椡丄栤戣傪夝寛偡傞椡摍偺堢惉傪栚巜偟偨庼嬈偺夵慞傪恑傔妛椡岦忋傪恾偭偰偒偨丅偦偺寢壥丄擔杮偺惗搆偺惓摎棪偼俁暘栰偱岦忋偟丄柍摎棪偼尭彮偟偨丅
丂俀侽侾俀擭偵弌戣偝傟偨悢妛揑儕僥儔僔乕俉俆戣偺擔杮偺惓摎棪偼丄俀侽侽俇擭偲偺嫟捠栤戣俁俇戣偵偮偄偰丄俁億僀儞僩崅偔側偭偨丅OECD暯嬒傪俋億僀儞僩忋夞偭偰偄傞丅傑偨丄柍摎棪偱偼俀侽侽俁擭偲偺嫟捠栤戣俁俇戣偵偮偄偰丄係億僀儞僩掅壓偟偨丅妛椡岦忋偑尒偊偰偒偨偲峫偊傜傟傞丅
丂俀侽侾俀擭偵弌戣偝傟偨撉夝椡係係戣偺擔杮偺惓摎棪偼丄OECD暯嬒傪俉億僀儞僩忋夞傝丄係俁戣偵偮偄偰丄俀侽侽俋擭傛傝俀億僀儞僩崅偔側偭偨丅傑偨丄暯嬒柍摎棪偵偮偄偰丄係俁戣偺偆偪係侾戣偱丄俀侽侽俋擭傛傝傕俀億僀儞僩掅壓偟偨丅壓夞偭偨俆戣偼偄偢傟傕乽帺桼婰弎乿偱偁傞丅俀侽侽侽乣俀侽侽俇擭傑偱偺柍摎棪偱丄壽戣偱偁偭偨乽帺桼婰弎乿丄偑夵慞偝傟偨偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅
丂俀侽侾俀擭偵弌戣偝傟偨壢妛揑儕僥儔僔乕俆俁戣偺擔杮偺惓摎棪偼丄OECD暯嬒傪俋億僀儞僩忋夞傝丄俀侽侽俇擭傛傝傕俁億僀儞僩崅偐偭偨丅
丂壢妛揑儕僥儔僔乕栤戣偺擔杮偺柍摎棪偼丄OECD暯嬒偲傎傏摨偠偱偁傞偑丄俀侽侽俇擭傛傝傕俀億僀儞僩掅偄丅壢妛揑側抦幆傪妶梡偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨偲峫偊傜傟傞丅
丂乮係乯惗搆偺嫽枴傗栚揑摍偺堄幆挷嵏乮幙栤巻挷嵏乯
丂PISA俀侽侾俀擭偱偼丄廳揰挷嵏懳徾偺悢妛揑儕僥儔僔乕偵偮偄偰丄惗搆偺嫽枴傗栚揑堄幆摍傪栤偆堄幆挷嵏傕峴傢傟偨丅悢妛揑儕僥儔僔乕偺堄幆挷嵏偑峴傢傟偨偺偼丄俀侽侽俁擭挷嵏埲棃俋擭傇傝偱偁傞丅
丂悢妛偵偮偄偰丄乽悢妛偵偍偗傞嫽枴丒娭怱傗妝偟傒乿乽悢妛偵偍偗傞摴嬶揑摦婡晅偗乿乽悢妛偵偍偗傞帺屓岠椡姶乿乽悢妛偵偍偗傞帺屓奣擮乿乽悢妛偵懳偡傞晄埨乿偺俆偮偺娤揰偵傛偭偰挷嵏傪偟偨丅
丂乽嫽枴丒娭怱丗庼嬈偑妝偟偄偐摍乿丄乽摦婡晅偗丗悢妛偼妛傃偑偄偑偁傞摍乿丄乽帺屓岠椡姶丗栤戣傪夝偔帺怣偑偁傞偐摍乿偼丄2003擭偲斾傋俀侽億僀儞僩掱搙偺忋徃偑尒傜傟丄夵慞偺偒偞偟偑尒傜傟傞丅乽帺屓奣擮丗悢妛偱偼椙偄惉愌傪偲偭偰偄傞摍乿偼丄2003擭傛傝悢億僀儞僩忋徃偟偨丅偟偐偟丄乽晄埨丗悢妛偺庼嬈偵偮偄偰偄偗側偄摍乿偱偼丄俀003擭偲曄傢傜側偄丅
丂偙偺傛偆偵丄擔杮偼乽晄埨乿傪彍偔係偮偺娤揰偱俀侽侽俁擭挷嵏偺悢抣傪忋夞偭偨丅偟偐偟丄OECD暯嬒偲斾傋傞偲俀侽乣係侽億僀儞僩掅偔丄埶慠偲偟偰乽庼嬈偵偮偄偰偄偗側偄乿偲怱攝偡傞惗搆偺妱崌偑懡偔丄悢妛偺嬯庤堄幆傕晜偒挙傝偵側偭偨丅
丂堄幆挷嵏偺寢壥偵偮偄偰暥晹壢妛徣妛椡挷嵏幒偱偼乽尓嫊偵摎偊傞偲偄偆擔杮恖偺崙柉惈傕偁傝丄堦奣偵懠崙丒抧堟偲斾傋傞偙偲偼偱偒側偄乿偲巜揈偟偮偮傕丄乽惗搆偺妛廗堄梸偼惉愌岦忋偵捈寢偡傞丅悢妛傊偺嬯庤堄幆傪暐怈偟丄栚揑堄幆傪崅傔傞傛偆側巤嶔傪恑傔偨偄乿偲偟偰偄傞丅
丂乽妛峑偵偍偗傞妛廗娐嫬乮悢妛偺庼嬈偺暤埻婥乯乿偵偮偄偰偼丄崙嵺暯嬒偵斾傋丄奺巜昗偱俆乣俀侽億僀儞僩傛偄忬嫷偵偁傞丅傑偨丄俀侽侽俁擭偵斾傋丄偄偢傟傕巜昗俆乣侾侽掱搙忋徃偟偰偄傞丅
丂擔杮偺乽惗搆偲嫵巘偺娭學乿偼丄俀侽侽俁擭偵斾傋椙岲側曽岦傊夵慞偝傟偨偙偲偑柧妋偵側偭偨丅
丂慡崙妛椡僥僗僩偺幙栤巻挷嵏偺寢壥偐傜傕丄帣摱惗搆偑乽妛傃乿偵栠偭偰偒偰偄傞條巕偑尒傜傟傞丅尵岅妶摦偺廩幚傪恾傞拞偱丄儕億乕僩偺嶌惉傗榑弎摍丄尵岅妶摦椡傪崅傔傞妛廗傕奺嫵壢偱幚巤偝傟傞傛偆偵側偭偰偒偨偐傜偱偁傞丅抦幆偺廗摼偵壛偊偰巚峫椡傗敾抐椡丄昞尰椡偺堢惉偵傕椡傪擖傟傛偆偲偡傞妛峑尰応偺搘椡偑丄PISA俀侽侾俀偺寢壥偵斀塮偝傟偨峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅
丂乮俆乯栤戣夝寛擻椡偼悽奅戞俁埵
丂暥晹壢妛徣偼俀侽侾係擭係寧侾擔丄OECD偑幚巤偟偨俀侽侾俀擭PISA偺拞偱峴側傢傟偨栤戣夝寛擻椡偵娭偡傞挷嵏寢壥傪敪昞偟偨丅
丂栤戣夝寛擻椡偺挷嵏偼丄僐儞僺儏乕僞乕傪巊偭偰幚巤偟偨丅帺摦寯攧婡偱愗晞傪攦偆摍丄恎嬤側栤戣傪夝偔擻椡傪挷傋偨丅擔杮偺栤戣夝寛擻椡偺暯嬒摼揰偼俆俆俀揰偱丄嶲壛偟偨崙偲抧堟偺拞偱戞俁埵丄侾埵偼俆俇俀揰偺僔儞僈億乕儖丄戞俀埵偼俆俇侾揰偺娯崙偲偄偆寢壥偵側偭偨丅擔杮偑乽栤戣夝寛擻椡乿偵岲惉愌傪廂傔偨偺偼丄妶梡椡丒墳梡椡傪廳帇偡傞PISA傪堄幆偟偨妛椡岦忋嶔偑幚傪寢傫偩寢壥偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅
俁丏PISA俀侽侾俀僩僢僾俁偲偺嵎偺夝徚傪栚巜偡偵偼
丂俀侽侾係擭俁寧俀俈擔丄撉攧怴暦偼乽慡崙偺岞棫彫拞妛峑偺偆偪丄崙偑掕傔偨昗弨帪悢傪挻偊偰丄庼嬈傪幚巤偟偰偄傞妛峑偼俈妱偵忋傞偙偲偑丄俀俇擔丄暥晹壢妛徣偺挷嵏偱傢偐偭偨丅乿偲曬偠偨丅挷嵏偼俀侽侾俁擭俉乣侾侽寧偵幚巤偟偨丅挷嵏寢壥偵傛傞偲丄彫妛峑俆擭偺昗弨帪悢俋俉侽帪娫乮侾僐儅係俆暘乯偲摨偠偑俁侽亾丄俈侽亾偼昗弨帪娫傛傝懡偔愝掕偝傟丄俀俆亾偼廡俀僐儅偺庼嬈傪峴偭偰偄傞丅拞妛峑侾擭偱偼丄昗弨帪悢侾侽侾俆帪娫乮侾僐儅俆侽暘乯偲摨偠偑俀俉亾偱丄俈俀亾偼昗弨帪悢傛傝懡偔丄俀俀亾偼廡俀僐儅埲忋懡偔庼嬈傪峴偭偰偄傞丅
丂昗弨帪悢偼丄乽嵟掅婎弨乿偲埵抲晅偗傜傟偰偍傝丄懡偔偺妛峑偑壞媥傒傗峴帠摍傪嶍彍偟偰丄昗弨埲忋偺帪悢傪妋曐偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅傑偨丄帣摱惗搆偺棟夝傗廗弉搙偵墳偠偨巜摫傪峴偭偰偄傞彫妛峑偼俉俁亾偱丄俀侽侾侾搙挷嵏偵斾傋傞偲俆億僀儞僩丄拞妛峑傕俈俋亾偱侾侽億僀儞僩憹偱偁偭偨丅
丂偙偺傛偆偵丄妛峑偑庡懱揑偵庼嬈帪悢傪憹傗偟丄庼嬈偺夵慞傪恑傔偰偄傞偙偲偑丄PISA俀侽侾俀偺惉愌傾僢僾偵宷偑偭偨偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丄僩僢僾俁偲偺嵎傪夝徚偟偰偄偔偵偼丄廗弉搙偵墳偠偨巜摫傪揙掙偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅掅埵憌偐傜忋埵憌傊妛椡傪崅傔傞偵偼丄偦傟偧傟偺廗弉搙偵偍偄偰丄帣摱惗搆偑妛廗撪梕傪棟夝偟偨傝丄抦幆傪帺傜妉摼偟偨傝偟偰丄廩幚姶傗枮懌姶傪傕偨偣丄師偺抜奒偵挧愴偟傛偆偲偡傞堄梸傪崅傔偰偄偔偙偲偑昁梫偱偁傞丅偦偟偰丄庼嬈偱妉摼偟偨抦幆傗媄擻傪丄擔忢惗妶偵妶梡偟偨傝丄怴偨側抦幆傪憂憿偟偨傝偡傞摍丄斈梡椡傪崅傔偰偔偙偲偑廳梫偱偁傞丅
丂拲侾丗嘆 崙嵺悢妛丒棟壢嫵堢挷嵏乮TIMSS丗Trends in International Mathematics and Science Study乯偲偼丄崙嵺嫵堢摓払搙昡壙妛夛乮IEA乯偑峴偆彫丒拞妛惗傪懳徾偲偟偨嶼悢丒悢妛媦傃棟壢偺摓払搙偵娭偡傞崙嵺斾妑嫵堢挷嵏偺偙偲偱偁傞丅
丂丂丂丂嘇 OECD惗搆偺妛廗摓払搙挷嵏乮PISA丗Program for International Student Assessment乯偲偼丄媊柋嫵堢廔椆抜奒偱恎偵偮偗偨抦幆傗媄擻偑幚惗妶偺條乆側応柺偱捈柺偡傞壽戣偵偳偺掱搙妶梡偱偒傞偐傪昡壙偡傞傕偺偱偁傝丄撉夝椡 悢妛揑儕僥儔僔乕丄壢妛揑儕僥儔僔乕傪庡懱偲偟偰挷嵏偺偙偲偱偁傞丅
丂拲俀丗俀侽侽俁丒俀侽侽俇擭偺挷嵏偵婲場偡傞丅俀侽侽侽擭偺擔杮偺崙嵺弴埵偼悢妛揑儕僥儔僔乕偑侾埵丄撉夝椡偑俉埵丄壢妛揑儕僥儔僔乕偑俀埵偲僩僢僾僋儔僗偩偭偨偑丄俀侽侽俇擭偺挷嵏偱偼悢妛揑儕僥儔僔乕偑侾侽埵丄撉夝椡偑侾俆埵丄壢妛揑儕僥儔丂丂丂僔乕偑俇埵偲媫棊偟丄嫵堢惌嶔偺尒捈偟傪媮傔傞惡偑崅傑偭偨丅
丂拲俁丗挷嵏暘栰偛偲偵丄挷嵏栤戣偺擄堈搙傪婎偵屄乆偺惗搆偺廗弉搙傪摼揰壔偟丄偦傟傪堦掕偺斖埻偱嬫愗偭偨傕偺傪廗弉搙儗儀儖偲屇傇丅
仧 嶲峫暥專丂
嘆 TIMSS1999 崙嵺斾妑寢壥偺奣梫乮昞娷傓乯 (PDF丗220KB)丂崙棫嫵堢惌嶔尋媶強
嘇 OECD惗搆偺妛廗摓払搙挷嵏乮PISA2012乯崙棫嫵堢惌嶔尋媶強
嘊 OECD惗搆偺妛廗摓払搙挷嵏乮PISA2000乣2009乯崙棫嫵堢惌嶔尋媶強
嘋乽崙嵺悢妛丒棟壢嫵堢摦岦挷嵏乿乽OECD惗搆偺妛廗摓払搙挷嵏乿僂傿僉儁僨傿傾
嘍 挬擔怴暦僨僕僞儖斉 嘐撉攧怴暦丂嘑嶻宱僯儏乕僗乮僨僕僞儖乯
嘒 採尵宆僯儏乕僗僒僀僩偺乽BLOGOS乿丂丂 丂丂丂
丂仧 嶲峫帒椏丗崙棫惌嶔尋媶強岞昞偺帒椏偵婎偯偄偰嶌惉 丂
丂
( 2014/04/26 婰)
埲 忋
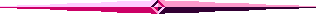
俿俷俹
|